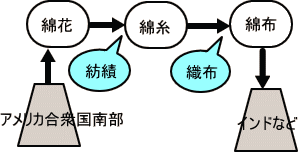
産業革命(第2部 5.) ホームへ戻る
1)農業革命(第2次囲い込み運動)
2)蒸気機関
3)木綿工業の機械化
4)軽工業から重工業へ
5)交通機関の発達
※問題と解答
1)農業革命(第2次囲い込み運動) トップ
・18世紀前半〜19世紀半ば、大地主が中小農民の土地や村の共有地を吸収して所有地面積を拡大した。
・大地主は農業資本家に土地を貸し、農業資本家は農業労働者を雇って農場を経営する、資本主義的大農経営が成立する。
・土地を失った中小農民は、都市に流入して工場労働者となった。
1709 イギリス議会が囲い込み法を制定(第2次囲い込み運動は議会が合法化した) 1730 ノーフォーク農法の開始
・大麦、クローヴァー、小麦、かぶらの順に4年周期で行う4輪作法。これにより穀物生産が増加した。
2)蒸気機関 トップ
・石炭で火を熾し、水を沸騰させ、水蒸気の力を機械の動力とした。
1710 ニューコメンの蒸気機関
・シリンダーと冷却器が共有されているため熱効率が悪く、炭坑の排水にしか用いられなかった。1769 ワットの蒸気機関
・シリンダーと冷却器を分離して熱効率を高める。ピストン運動を回転運動に転換して動力として実用化される(動力革命)
3)木綿工業の機械化 トップ
・綿花を紡いで綿糸とし(紡績)、綿糸を織って綿布とする(綿織物)ことにより、衣服などを作る工業。
・綿花の輸入先:アメリカ大陸(北アメリカ南部、カリブ海諸島)など
・綿布の輸出先:インド(19世紀後半にイギリスの植民地となる)
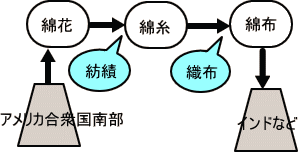
<綿花処理の機械> 1793 ホイットニー(米) 綿繰り機(綿の種の除去を容易にする)
<紡績の機械>1764 ハーグリーヴズ ジェニー(多軸)紡績機(ローラーの利用により1人で8本を紡ぐ) 1769 アークライト 水力紡績機(蒸気機関を利用。工場制大量生産の開始) 1779 クロンプトン ミュール紡績機(細くて強い糸を紡ぐことができる)
<綿織物の機械>1733 ジョン・ケイ 飛び杼(横糸を通す道具を自動的に動かす。従来の2倍の能力) 1785 カートライト 力織機(蒸気機関を利用。飛び杼の3.5倍の能力)
4)軽工業から重工業へ トップ
・木綿工業の機械化は機械を生産する機械工業を促し、機械工業は鉄を原料とするので製鉄業を促し、製鉄業は石炭を燃料とするので炭坑業を促した。
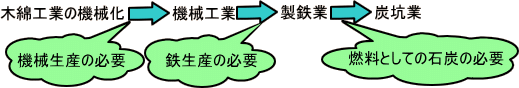
1709 ダービー 石炭による製鉄法を開発
5)交通機関の発達 トップ
・工業化は、原料や商品の運搬のため、交通の発達を促した。
<鉄道> 1804 トレヴィシック 蒸気機関車の発明(牽引力弱い) 1814 スティーヴンソン 蒸気機関車の試作(実用化しうる性能)(交通革命) 1825 スティーヴンソンの蒸気機関車がストックトン・ダーリントン間を走る 1830 リヴァプール(貿易港)・マンチェスター(木綿工業)間の実用運転開始
・鉄道の開通年:米(1830)、仏(1832年)、独・ベルギー(1835年)、露(1838年)、オランダ・イタリア(1839年)
<船> 1807 フルトン 蒸気船の発明(クラーモント号がハドソン川を航行) 1819 サヴァンナ号がアメリカ大陸からヨーロッパへと大西洋を横断(積み荷は綿花)