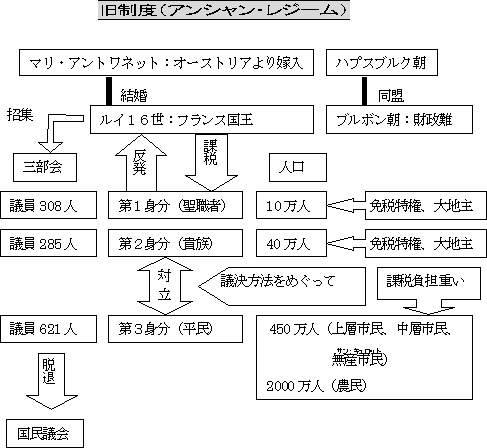
市民革命(アメリカ独立革命、フランス革命)<第2部 6.> ホームへ戻る
<1>アメリカ独立革命
<2>フランス革命
(1) 旧制度(アンシャン・レジーム):革命前のフランス社会
(2) 国民議会 1789.6-1791.9 ←三部会より分離
(3) 立法議会 1791.10-92.9 ←1791年憲法に基づく制限選挙
(4) 国民公会 1792.9-95.10 ←男子普通選挙
(5) 総裁政府 1795.10-1799.11 ←制限選挙
◎前へ(第2部 2.近代ヨーロッパ②)
◎後ろへ(第2部 7.19世紀前半の欧米)
※問題と解答
<1>アメリカ独立革命 トップ
1 イギリスの北アメリカ植民地支配 1607年 ヴァージニア:最初の植民地 1620年 ピューリタンの一団(ピルグリムファーザーズ)がプリマスに上陸→イギリスからの移民増加 1733年 ニューイングランド植民地13州の成立 ・イギリスはニューイングランド植民地への課税を強める。植民地はそれに反発。 1765年 イギリス議会が印紙法を制定←植民地は「代表なくして課税なし」と主張して反発 1773年 イギリス議会が茶法を制定←植民地はボストン茶会事件を起こして反発 1774年 植民地は大陸会議(第1回フィラデルフィアで)を開く 2 独立戦争(1775-83年) 1775年 レキシントンの戦い:13植民地軍(総司令官ワシントン)vsイギリス軍 1776年 トマス・ペイン「コモン・センス」:独立の世論を高める(1月) 独立宣言(起草者トマス・ジェファソン)(7月4日) 1777年 国名をアメリカ合衆国とする ・植民地の同盟国:フランス(1778年)、スペイン、オランダ ・中立国:ロシアが中心となり武装中立同盟を結成(1780年) 1781年 ヨークタウンの戦い:植民地軍の勝利確定 1783年 パリ条約
・イギリスがアメリカ合衆国の独立を承認
・イギリスがアメリカ合衆国にミシシッピ川以東のルイジアナを割譲3 憲法制定 1787年 合衆国憲法
・連邦主義、大統領制、三権分立、国民主権
・初代大統領ワシントン
<2>フランス革命 1789-99年
(1)旧制度(アンシャン・レジーム):革命前のフランス社会 トップ
a) 身分制度
・第1身分:聖職者、12万人、0.5%、特権身分(免税などの特権あり)
・第2身分:貴族、40万人、1.5%、特権身分(免税などの特権あり)
・第3身分:平民、2500万人、98%、課税負担
都市民(約500万人):上層市民、中層市民、無産市民(サン・キュロット)
農民(約2000万人):大借地農、自営農民、貧農、折半小作農・雇農
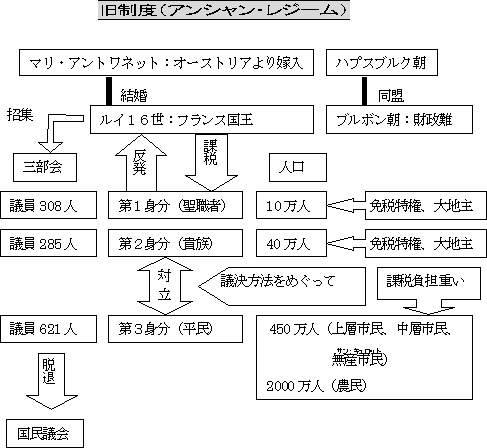
b) 王室財政の危機
・ルイ14世以来の宮廷費や戦費、アメリカ独立革命への援助、貴族への年金などで、王室財政は赤字に
・国王ルイ16世はテュルゴー(経済学者)、ネッケル(スイスの銀行家)を起用して財政改革を試みるが、特権身分への課税案に特権身分が反発
1774 テュルゴー 財務総監に任命される(~1776) 1777 ネッケル 財務総監に任命される(~1781、1788~89) 1786 英仏通商条約 フランス市場をイギリスに開放したため、イギリスの工業製品がフランスに流れ込み、フランスの工業が不振となった 1787 カロンヌ 名士会を開いて特権身分への課税を試みたが失敗 1789 アベ・シェイエス パンフレット「第三身分とは何か」刊行
・”第三身分はすべてである”と主張して特権身分を攻撃
(2) 国民議会 1789.6-1791.9 ←三部会より分離 トップ
*上層市民が中心、立憲君主主義、指導者:ミラボー、ラファイエット
・特権身分は国王の権限を制限しようとして、特権身分は国王に三部会の開催を要求した。
・三部会は身分制議会で、第1身分代表約300名、第2身分代表約300名、第3身分代表約600名の計約1200名より成り立っていた。
・第1,2身分代表は身分別議決(1身分1票)を主張し、第3身分代表は個人別議決(1人1票)を主張したため、三部会は開会当初から40日間空転する。
1789 5.5 三部会の招集(ヴェルサイユ宮殿で) 6.17 第3身分代表らが国民議会の設立を宣言する 6.20 球技場(テニスコート)の誓い
・国民議会の議員が憲法制定までは国民議会を解散しないと誓い合う6.27 国王ルイ16世が国民議会を承認 7.9 国民議会は憲法制定国民議会と改称し憲法制定に着手する 7.11 国王ルイ16世が財務総監ネッケルを罷免 7.14 パリ市民がバスティーユ牢獄を襲撃 7-8月 農民一揆が全国に広がる「大恐怖」
・農民による領主の館の襲撃、土地台帳の焼き捨て、高利貸しの襲撃などが続く8.4 国民議会が封建的諸特権の廃止を採択←農民一揆の広まりを抑えるため
・無条件(無償)廃止:封建的身分支配、教会への十分の一税、領主裁判権など
・条件付(有償)廃止:封建的地代(つまり年貢。25年分の年貢を一括納入すれば土地所有者として認められる)8.24 国民議会が人権宣言(人間と市民の権利の宣言)を採択
・起草者ラファイエット、17ヶ条、自由・平等、自由・財産の安全、圧政への抵抗権、国民主権、法の支配、言論・出版の自由、私有財産の不可侵10.4-5 ヴェルサイユ行進
・国王にパンを要求する中央市場や場末街の女性がヴェルサイユ宮殿まで行進し、国王一家をパリへ連れ帰る。これにより、国王と国民議会はパリ民衆の監視下におかれることになる。11.2 教会財産の国有化 12.5 アッシニア紙幣の発行
・教会財産を担保にして発行される1790 7.12 聖職者基本法
・聖職者を公務員として政府の監督下におく1791 4.2 ミラボーの死
・国王と議会の調停にあたっていたミラボーの死によって、国王は革命の急進化に不安を大きくする。6.14 ル・シャプリエ法(団結禁止法)
・労働者や職人の団結・ストを禁止6.21-22 ヴァレンヌ逃亡事件
・国王一家がパリを脱出して王妃の故国オーストリアを目指したが、国境付近のヴァレンヌで捕まりパリへ連れ戻された事件。
・これにより、国民の間では国王への不信が募り、共和主義者(王政を廃止する考えの人)が勢力を増す。8.27 ピルニッツ宣言
・オーストリア帝国(皇帝レオポルト2世、フランス王妃マリ・アントワネットの兄)とプロイセン王国がフランス革命政府に対してフランス革命政府に対してフランスへの武力干渉を示唆する。9.3 1791年憲法の制定
・立憲君主主義(王権を制限した立憲政治)、制限選挙(選挙権に財産資格を付ける)、一院政
(国王は「停止的」拒否権をもつ:議会が可決した法案の裁可を一定期間拒否しうる)
(受動市民:市民権のみを持つ、能動市民:一定資産を有して政治に参加しうる)
(3) 立法議会 1791.10-92.9 ←1791年憲法に基づく制限選挙 トップ
*フイヤン派:立憲君主主義、上層市民、自由主義貴族、ラファイエット、バルナーヴ
*ジロンド派:穏健共和主義、中層市民
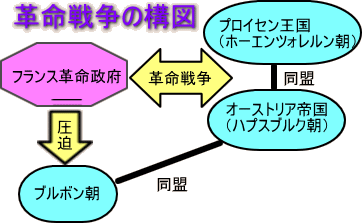
【参照】立法議会(歴史用語解説・英文付き)
1791 10.31 亡命貴族(エミグレ)の財産没収 1792 3.23 ジロンド派内閣の成立 4.20 フランス革命政府がオーストリアに宣戦布告
・フランスVSオーストリア・プロイセン連合、革命戦争始まる
・ジロンド派内閣は倒れ、フイヤン派内閣が成立7.11 立法議会は「祖国の危機」を宣言して全国から義勇兵を募る 7.25 プロイセン軍司令官ブラウンシュバイク公のコブレンツでの宣言(フランス国王への危害があればパリ市を破壊する) 8.10 パリ民衆と義勇兵がテュイルリー宮殿を攻撃
・立法議会は王権を停止、普通選挙による国民公会の招集を布告
・国王はタンプル宮に幽閉される
・パリにコンミューンという民衆組織ができ、パリの実権を握る9.2-6 「9月の虐殺」
・コンミューンの指導により、パリ民衆が監獄に収容されていた反革命容疑者を人民裁判により虐殺9.20 ヴァルミーの戦い
・フランス革命軍がプロイセン軍を撃退
・プロイセン軍に従軍していた文豪ゲーテの言葉
「ここから、そしてこの日から、世界史の新しい時代が始まる」
(4) 国民公会 1792.9-95.10 ←男子普通選挙 トップ
*平原派:中間派
*ジロンド派:穏健共和主義、中層市民
*ジャコバン派(山岳派):急進共和主義、下層市民、マラー、エベール、ロベスピエール、ダントン
*ジロンド派政権
1792 9.20 国民公会の招集(普通選挙) 9.21-22 王政廃止、共和政宣言(第1共和政の成立) 1793 1.21 ルイ16世の処刑(革命広場にて、ギロチンにより) 2.13 第1回対仏大同盟(~1797)
・イギリス(首相小ピット)の呼びかけ
・ロシア、オーストリア、プロイセン、スペイン、オランダ、ポルトガル、サルデーニャなどが参加
・反フランス、反革命の同盟2.24 徴兵制の採用(30万人の募兵) 3.10 ヴァンデーの農民反乱
・ヴァンデー県で王党派の指導する農民反乱が起きる
革命裁判所の設置
・政治犯を審理、1793年秋頃から本格的に始動4.6 公安委員会の設置
・国民公会内に組織され、事実上の政府となる。
・革命裁判所、監視委員会、国民公会の委員により構成される。
・7月にロベスピエールが加盟。5.4 最高価格令
・必需品、賃金などに最高価格を定めて経済統制をする。
*ジャコバン派の独裁 1793.6-1794.7
1793 6.2 ジャコバン派がジロンド派を国民公会から追放して独裁権力を握る 6.24 1793年憲法(ジャコバン憲法)の採択
・主権在民、人民の生活権・労働権、男子普通選挙、革命権、を認める。
・10月に実施予定だったが延期され、結局実施されないままに終わる。7.7 封建的諸特権の無償廃止:領主権の無条件(無償)廃止
・自作農の創出、農民は保守化して革命に対して消極的に7.13 マラーがジロンド派のシャルロッテ・コルデーによって暗殺される 8.1 メートル法の採用 10.5 革命暦(共和暦)の採用 10.16 王妃マリ・アントワネット処刑 11.10 理性の崇拝の祭典始まる 1794 3-4月 エベール(左派)やダントン(右派)処刑、ロベスピエールの独裁確立 6 プレリアール法
・革命裁判の迅速化のため、弁護・証人・予審の省略が可能に。7.27 テルミドール9日の反動
・反ロベスピエール派のクーデタにより、ロベスピエール派は翌日処刑。
・ジャコバン派独裁は終わり、テルミドール派(旧ジロンド派)が実権を握る。
*テルミドール派政権
(5) 総裁政府 1795.10-1799.11 ←制限選挙 トップ
*テルミドール派が実権を握る穏健な共和主義。
*弱体政府なため反政府反乱が続発。その反乱を鎮圧する軍部の発言力が強まる。
1795 8.22 1795年憲法(共和国第3年憲法):制限選挙、2院政、5人の総裁制 10.5 ヴァンデミエールの王党派の反乱
・ナポレオンの指揮する陸軍に鎮圧される10.27 総裁政府の成立 1796 3.11 ナポレオンのイタリア遠征(~1797):フランス軍がオーストリアに勝利 5.27 バブーフの陰謀
・私有財産制度の廃止を主張して反政府の武装蜂起を計画
・武装蜂起の実施前に逮捕・処刑される1797 10.17 カンポ・フォルミオの和約:オーストリアとの講和条約
・フランスがロンバルディア、ベルギーを獲得。
・オーストリアがヴェネツィアを獲得。
・第1回対仏大同盟の崩壊1798 5.19 ナポレオンのエジプト遠征(~1799):イギリスと戦う
・イギリスとインドとの通路を絶つ目的で実施。
・陸上の戦いでは勝利するが、アブキール湾の戦いではイギリスに敗北。
・ロゼッタ・ストーンを発見(エジプト文字解読の手がかりとなる)1799 6.1 第2回対仏大同盟
・イギリス、オーストリア、ロシアなど11.9 ブリュメール18日のクーデタ
・ナポレオンのクーデタ。総裁政府を倒す。
・シェイエス、タレーラン、フーシェらがナポレオンに協力。