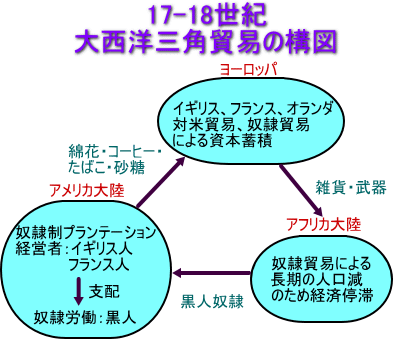
近代ヨーロッパ②17・18世紀(絶対主義、イングランド革命)<第2部 2.> ホームへ戻る
<1>スペイン王国とネーデルラント独立
①ハプスブルク朝スペイン王国の繁栄
②ネーデルラント独立戦争
<2>イングランド王国 テューダー朝 1485-1603
<3>フランス王国 ブルボン朝 1589-1793
①初代:アンリ4世(位1589-1610)
②2代:ルイ13世(位1610-43)
③3代:ルイ14世(位1643-1715)
④4代:ルイ15世(位1715-74)
<4>神聖ローマ帝国
<5>プロイセンとオーストリア
①プロイセン王国 ホーエンツォレルン朝 ルター派
②オーストリア ハプスブルク朝 カトリック
③プロイセンとオーストリアの戦争(イギリスとフランスの戦争)
<6>ロシア帝国 ロマノフ朝 1613-1917
<7>ポーランド分割 1772-95
<8>イングランド革命
①ピューリタン革命 1642年
②イングランド共和国 1649-60
③王政復古 1660-
④名誉革命 1688年
⑤大ブリテン王国 1707-1801
<9>アメリカ大陸
①中南部:インディオの奴隷化
②北部:インディオを追放
◎後ろへ(第2部 1.近代ヨーロッパ①)
◎前へ(第2部 5.産業革命 6.市民革命)
※問題と解答
<1>スペイン王国とネーデルラント独立
①ハプスブルク朝スペイン王国の繁栄 トップ
*カルロス1世(位1516-56)→神聖ローマ皇帝を兼任(ドイツではカール5世と名乗る)
1520 コムネーロスの反乱(カルロス1世の即位に反対する都市の反乱)←鎮圧
1494-1544 イタリア戦争を続行
1556 引退
→フェリペ2世(子):スペイン王位(スペイン・ハプスブルク)
→フェルディナンド1世(弟):神聖ローマ皇帝位(オーストリア・ハプスブルク)
*2代:フェリペ2世(位1556-98)
1559 カトー・カンブレジ和約:イタリア戦争終結
【異端弾圧】
・異端審問制による非カトリックへの弾圧
・外国書籍の輸入禁止、出版規制
【繁栄】
1571 レパント沖の海戦:オスマン帝国を破る
1580 ホルトガルを併合→「太陽の没することのない」世界帝国
・アメリカ大陸からの銀の流入(ペルーのポトシ銀山、メキシコのサカテカス銀山など)
【衰退】
・アメリカ大陸からの銀の流入減少(17世紀初めより)
・毛織物工業の衰退←イスラーム信者の追放
1566 ネーデルラントのカルヴァン派が乞食党(ゴイセン)を結成→ネーデルラント独立運動
1588 スペインの無敵艦隊(アルマダ)がイギリス海軍に敗北
1640 ポルトガル独立(ブラガンサ朝)
②ネーデルラント独立戦争 トップ
【独立運動前】
・アントワープ市の繁栄、毛織物工業、カルヴァン派
・スペイン国王フェリペ2世はカトリックを強制し、異端審問によりプロテスタント弾圧
【独立運動の展開】
1566 ネーデルラントのカルヴァン派が乞食党(ゴイセン)を結成
→スペイン国王フェリペ2世は、アルバ公を派遣して弾圧
→南部のフランドル・ブラバントから北部ネーデルラントやヨーロッパ各地に亡命者多数
1568 ネーデルラント独立戦争起こる(-1648)
・独立軍指導者:オラニエ公ウィレム
1576 ガンの和平→しかし、戦闘は継続
1576 ネーデルラント南部10州がアラス同盟を結成してスペインと講和
1579 ネーデルラント北部7州がユトレヒト同盟を結成してスペインと抗戦
1581 ネーデルラント連邦共和国の独立宣言
・イギリスは独立派を支援
【参照】ユトレヒト同盟(歴史用語解説・英文付き)
1585 スペイン軍、アントウェルペン占領、ネーデルラント商工業の中心は南部から北部へと移動
・毛織物:フランドル→ライデン
・貿易・金融:アントワープ→アムステルダム
1609 独立戦争休戦、事実上の独立達成
1648 ウェストファリア条約:国際的に独立承認
【貿易の繁栄】
1602 オランダ東インド会社の設立
・東南アジアの香辛料貿易
・北アメリカのニューネザーランド植民地
・奴隷貿易
・首都アムステルダムはヨーロッパの金融貿易の中心(1609 アムステルダム銀行設立)
・ライデンの毛織物工業、ホラント州の造船業、北海の漁業、デルフトの陶器業、マース河畔の醸造業
【文化の繁栄】
1625 グロティウス「戦争と平和の法」:国際法
(美術)ルーベンス、レンブラント:バロック様式
1700 スペイン王国でハプスブルク朝断絶、ブルボン朝成立(-1931)
<2>イングランド王国 テューダー朝 1485-1603 トップ
*初代:ヘンリ7世(位1485-1509)
・星室庁の設置(国王直属の特別裁判所)
・貨幣・度量衡の統一→流通の円滑化
・ジェントリ(地主階級)を官僚として採用し、封建貴族を抑える
・ジェントルマン(ジェントルと貴族)
*2代:ヘンリ8世(位1509-47)
【イングランド国教会】
1534 首長法:イングランド国教会の成立
・カトリック教会からの離脱
・国教会の首長は国王
・修道院の解散、土地財産の没収→王室財政の強化
・10分の1税など教会関係の税収はイギリス国王に
【毛織物工業】
・アントワープ向け毛織物輸出増
・第1次囲い込み(エンクロージャー):羊毛確保のため
→開放耕地や共有地を統合し、垣根で囲って個人所有地とすること
→耕地を牧場に転換する(トマス・モア「羊が人間を食う」)
*3代:エドワード6世(位1547-53)
*4代:メアリ1世(位1553-58)
・スペイン国王フェリペ2世と結婚
・1555 カトリック復活
*5代:エリザベス1世(位1558-1603)
1559 統一法:国教会の確立、他宗派禁止
1588 アルマダ海戦:スペイン無敵艦隊に勝利
1600 東インド会社の設立:アジア貿易のため
【グレシャム】
・トマス・グレシャム:貨幣改鋳、通貨安定
→グレシャムの法則「悪化は良貨を駆逐する」
・ポンド高、アントワープ市場閉鎖→毛織物輸出減→失業者増→救貧法(1601)
【イギリス・ルネサンス】
・シェークスピア(1564-1616)の劇作「オセロ」「マクベス」「リヤ王」「ハムレット」
【北アメリカ植民】
・ウォーター・ローリーの植民
1607 ジェームズタウン植民地
1620 ピルグリム・ファーザーズがメイフラワー号でニューイングランドへ
<3>フランス王国 ブルボン朝 1589-1793 トップ
*ユグノー戦争 1562-98
・ユグノー:カルヴァン派、貴族・手工業者など
・国王シャルル9世、摂政カトリーヌのユグノー抑圧→戦争勃発
・カトリックVSユグノー(フランスのカルヴァン派)の宗教戦争
1572 サン・ヴァルテルミの虐殺:カトリック派がプロテスタントを虐殺
【3人のアンリ】
・国王派:アンリ3世(位1574-89)(ヴァロワ朝最後)→暗殺(1589)
・カトリック派:アンリ・ド・ギーズ→暗殺(1588)
・カルヴァン派:アンリ・ド・ブルボン→アンリ4世
1589 ヴァロワ朝断絶、ブルボン朝成立(-1793)
①初代:アンリ4世(位1589-1610) トップ 【参照】(史料)ナントの勅令(歴史用語解説)
1593 ブルボン家はカトリックに改宗
1598 ナントの勅令:カルヴァン派に信仰の自由と市民権を与える→ユグノー戦争終結
・カトリックとプロテスタントとの共存
・中小貴族を積極的に登用、大貴族を押さえる
・シュリーを財務官に起用
1604 東インド会社
②2代:ルイ13世(位1610-43) トップ
【宰相リシュリュー(1624-43)】
・絶対王政の確立、全国三部会を招集せず
・反ハプスブルク政策、三十年戦争に参加(1635-)
③3代:ルイ14世(位1643-1715) トップ
【宰相マザラン(1643-61)】
1648 フロンドの乱(-53):貴族による反乱、反乱鎮圧後、王権確立
【ルイ14世の親政(1661-1715)】
(1)財務総監コルベールの重商主義政策(コルベリズム)
・貿易差額(出超)による貴金属の蓄積
・王立工場(マニファクチュア)の設立
・保護貿易(関税高)による工業育成
・東西インド会社への助成
(2)ヴェルサイユ宮殿の造営:バロック様式
・フランス語がヨーロッパの上流社会に流通
(3)王権神授説、「朕は国家なり」、太陽王の理念
(4)ナントの勅令廃止(1685):カルヴァン派の国外逃亡
(5)対外戦争
a.ネーデルラント継承戦争(フランドル戦争) 1667-68
b.オランダ戦争 1672-78
c.ファルツ継承戦争 1688-97 (ヨーロッパ)ブルボンVSハプスブルク
【ウィリアム王戦争 1689-97 (北アメリカ)フランスVSイギリス】
d.スペイン継承戦争 1701-13 (ヨーロッパ)
フランス・スペインVSオーストリア・イギリス・オランダ
【アン女王戦争 1702-13 (北アメリカ)フランスVSイギリス】
1713 ユトレヒト条約
1:スペイン・ブルボン朝の承認(スペインとフランスの合同は認めず)
2:イギリス領拡大
・ヨーロッパ:ジブラルタル、ミノルカ島(スペインより)
・北アメリカ:ハドソン湾、ニューファンドランド、アカディア(フランスより)
3:オーストリア領拡大
・ヨーロッパ:南ネーデルラント、ミラノなど(スペインより)
④4代:ルイ15世(位1715-74) トップ
1747 オランダ侵略
・啓蒙思想起こる
1748 モンテスキュー「法の精神」
1751 百科全書の刊行始まる(ディドロ、タランベール)(-72)
1751 J・J・ルソー「人間不平等起源論」
{ 17世紀の危機:ヨーロッパ経済の縮小・下降 }
・対外進出の停滞、貿易減、物価下落
・「魔女狩り」
・ピューリタン革命(イギリス)、フロンドの乱(フランス)、カタルーニャ反乱(スペイン)など起きる
・アメリカ大陸からの銀流入減
・気温低下
<4>神聖ローマ帝国 トップ
*三十年戦争 1618-48 ドイツを舞台とした国際的な宗教戦争
【対立】
・ドイツのカトリック派諸侯VSプロテスタント派諸侯
・ハプスブルク朝(神聖ローマ皇帝オーストリア、スペイン国王、カトリック)VSブルボン朝(フランス国王、カトリック)
・神聖ローマ皇帝VSデンマーク国王、スウェーデン国王(ルター派)
【経過】
1618 神聖ローマ皇帝がボヘミア国王にカトリック教徒を任命、ボヘミアのプロテスタントがそれに反発して蜂起
1:ベーメン・ファルツ戦争 1618-23
2:デンマーク戦争 1625-29 皇帝派ヴァレンシュタインの活躍
3:スウェーデン戦争 1630-35 スウェーデン国王グスタフ・アドルフ
・バルト海をめぐる覇権争い
1632 リュッツェンの戦い:グスタフ・アドルフがヴァレンシュタインに敗北
4:フランス戦争 1635-48
【結果】
1648 ウェストファリア条約
・国際条約の最初
・ルター派、カルヴァン派の信仰の自由
・スイス、オランダの独立を承認
・神聖ローマ帝国内の領邦君主は主権国家として独立(神聖ローマ帝国は事実上解体)
<5>プロイセンとオーストリア
①プロイセン王国 ホーエンツォレルン朝 ルター派 トップ
・ユンカー(領主貴族)が官僚・軍・農場を支配
*2代:フリードリヒ・ヴィルヘルム1世(位1713-40)
・軍国主義、王権強化
*3代:フリードリヒ2世(哲人王 位1740-86)
【啓蒙専制君主】
・啓蒙思想の影響を受け、近代化のために上からの改革を試みた絶対君主
・ヴォルテールらフランスの啓蒙思想家と親交を結ぶ(1750-53 ヴォルテールがサンスーシ宮殿に逗留)
・「国王は国家第一の下僕」(「反マキャベリ論」)
・王領地の農奴解放、賦役軽減、宗教的寛容、司法・教育の改革など
・サン・スーシ宮殿:ポツダム、ロココ式(1747 造営)
②オーストリア ハプスブルク朝 カトリック トップ
1699 カルロヴィッツ条約:オスマントルコからハンガリーを獲得
・多民族国家
*マリア・テレジア(位1740-80)
1740-42 第1次シュレジェン戦争
1744-45 第2次シュレジェン戦争
・中央集権化、行政・軍政・税制改革
*ヨーゼフ2世(位1765-90):啓蒙専制君主
・宗教的寛容令(イエズス会の追放)、貴族への課税、農奴解放の試み(81)
・疾風怒涛(シュトルム・ウント・ドランク)
1778 バイエルン継承戦争(-79)
③プロイセンとオーストリアの戦争(イギリスとフランスの戦争) トップ
*オーストリア継承戦争 1740-48 (ヨーロッパ)
・オーストリア・イギリスVSプロイセン・フランス・スペイン・バイエルン・ザクセン
1740 マリア・テレジア即位←プロイセンが異議
【ジョージ王戦争 1744-48 (北アメリカ) イギリスVSフランス】
1748 アーヘンの和約
1:プロイセンはオーストリアからシュレジェン地方を獲得
2:スペインはオーストリアからパルマ、ピァツェンツァを獲得
3:各国はプラグマティッシェ・ザンクティオン(国事勅令:皇帝カール6世がマリア・テレジアを相続人として定める)を確認
フランツ1世(位1745-65):ハプスブルク・ロートリンゲン朝成立
*七年戦争 1756-63(ヨーロッパ)
・プロイセン・イギリスVSオ-ストリア・フランス・ロシア・スウェーデン
・「外交革命」:ハプスブルクとブルボンが同盟
【フレンチ・インディアン戦争 1755-63 (北アメリカ)イギリスVSフランス】
【参照】パリ条約(1763年)(歴史用語解説・英文付き)
1763 フベルトゥスブルク条約←七年戦争
・オーストリアはシュレジェン奪回を放棄
1763 パリ条約←フレンチ・インディアン戦争
1:イギリス領拡大
・カナダ、ミシシッピ川以東のルイジアナ、セネガル、ドミニカを獲得(フランスより)
・フロリダを獲得(スペインより)
2:スペイン領拡大
・ミシシッピ川以西のルイジアナを獲得(フランスより)
<6>ロシア帝国 ロマノフ朝 1613-1917 トップ
*ミハイル・ロマノフ(位1613-45)
1667~ ステンカ・ラージンの反乱
*ピョートル1世(大帝 位1682-1725)
・西ヨーロッパ化政策(ユリウス暦の採用、学校・新聞など創設、西欧風生活の強制)
・武器・造船など西欧技術の採用
・軍備強化、税制改革、農奴制強化
1689 ネルチンスク条約:清との国境確定
1712 新都ペテルブルク(ネヴァ川河口)
【北方戦争(1700-21:スウェーデンVSロシア)】
・バルト海支配をめぐって
1709 ポルタヴァの戦い:ロシア優勢に
・バルト海東岸に進出
1721 ニスタット条約:ロシア勝利
*イヴァン6世(位1740-41)
*エリザベス女帝(位1741-62)
1741-43 スウェーデンと戦争
1742 フィンランドを占領
1743 オーボ条約:対スウェーデン
*エカチェリーナ2世(位1762-96):啓蒙専制君主
・フランスの啓蒙思想家との交流(ヴォルテール、ディドロ、タランベールらと文通、ディドロを招く)
・農奴制の強化、完成
・ラクスマンが日本に
1768 第1回露土戦争(-74):黒海北岸を領有
1773 プガチョフの乱(-75):以後、反動化
1780 武装中立同盟:アメリカ独立戦争に介入せず
1783 クリム・ハン国併合
1787 第2回露土戦争(-92):ヤッシー条約(92)ドニエストル河口を国境
1788 スウェーデンとの戦争(-90)
【参照】コサック(歴史用語解説・英文付き)
<7>ポーランド分割 1772-95 トップ
・再版農奴制:貴族層が農奴制を強めつつ穀物を生産し、西ヨーロパに輸出
*第1回ポーランド分割 1772
・プロイセン王国:フリードリヒ2世(位1740-86)
・ロシア帝国:エカチェリーナ2世(位1762-96)
・オーストリア:ヨーゼフ2世(位1765-90)
*第2回ポーランド分割 1793
・プロイセン王国:フリードリヒ・ヴィルヘルム2世(位1786-97)
・ロシア帝国:エカチェリーナ2世(位1762-96)
・オーストリアは不参加
・ポーランドではコシューシコが活躍
*第3回ポーランド分割 1795
・プロイセン、ロシア、オーストリアによる分割→ポーランド消滅
<8>イングランド革命 トップ
*ステュアート朝 1603-49/1660-1714←スコットランドより
【初代:ジェームズ1世(位1603-25)】
・王権神授説
・スコットランドとは同君連合
・ジェントルマン、ヨーマンの間にピューリタン主義が広まる
【2代:チャールズ1世(位1625-49)】
・専制政治を強める
①ピューリタン革命 1642年 トップ
1628 権利の請願
・議会の同意しない課税の禁止、不法な逮捕・投獄の禁止を国王に求める
1629 国王チャールズ2世は議会を解散(-40)
・ロード・ストラッフォード体制:国教会との結び付きを強める政治
・国王は国教会を強制、ピューリタン(イングランドのカルヴァン派)が抵抗
1639 スコットランドのカルヴァン派(長老派)反乱
→鎮圧のため、戦費調達の必要→議会招集の必要
1640 国王チャールズ2世は議会を召集(短期議会)
・議会は国王を非難、国王は議会を3週間で閉鎖
1642 ピューリタン革命(-49)
・議会派と王党派との武力衝突
・議会派内の党派
長老派:議会多数、和平、国教会体制、制限君主制、議会主権
独立派:軍の幹部、抗戦、ピューリタン、共和政、議会主権
水平派:軍の一般兵士、人民主権
・クロムウェル(独立派):鉄騎兵、新型軍
1645 ネーズビーの戦い:議会派の勝利
1646 内乱終結
1648 独立派が長老派を議会から追放、独立派の議会独占
1649 チャールズ1世処刑
②イングランド共和国 1649-60 トップ
【クロムウェルの政権(1649-58):独立派独裁、ピューリタニズム】
1649 水平派(指導者:リルバーン)の弾圧、アイルランド征服戦争
1651 航海法:オランダ船のイングランドからの閉め出し
1652 第1次英蘭戦争(-54):イギリスがオランダを破る
1653 クロムウェルが護国卿に就任、クロムウェル独裁はじまる
・ピューリタニズムに基づく政治:劇場閉鎖、娯楽禁止など
1658 クロムウェル死
③王政復古 1660- トップ
・王党派と長老派が結んで、チャールズ2世を即位させる(ステュアート朝復活)
【3代:チャールズ2世(位1660-85)】
・ブレダ宣言:革命関係者の責任不問、没収地は議会の決定に従う、信仰の自由など
・国王は国教会体制を拒否、カトリック化をねらう
1664 第2次英蘭戦争(-67)
1672 第3次英蘭戦争(-74):オランダの海上貿易の衰退
1673 審査法:公職に就く者は国教会信徒のみ
1679 人身保護法:不法逮捕の禁止
【4代:ジェームズ2世(位1685-88)】
④名誉革命 1688年 トップ
1688 名誉革命
・議会はオランダ総督ウィレムとその妻メアリを国王として招く
・ジェームズ2世は国外亡命
【5代:ウィリアム3世、メアリ2世(位1689-1702/1694):共同統治】
1689 権利の章典:議会による政治が確立
・国王が、議会の提出した権利の宣言を承認し、権利の章典として発布
・王権の制約、議会主権の立憲政治が確立、絶対王政の消滅
⑤大ブリテン王国 1707-1801 トップ
【6代:アン女王(位1702-14)】
1707 イングランド王国とスコットランド王国が合併
*ハノーヴァー朝 1714-現在←ドイツのハノーヴァーより
【初代:ジョージ1世(位1714-27)】
1721 ウォルポール(ホイッグ党)内閣:責任内閣制、「国王は君臨すれども統治せず」
・ホイッグ党とトーリー党
<9>アメリカ大陸
①中南部:インディオの奴隷化 トップ
*スペインの植民地(ブラジルのみポルトガルの植民地)
・銀鉱山
・プランテーション:砂糖、コーヒー、タバコ(ヨーロッパ向け輸出)
・労働力:インディオ、「黒人奴隷」(アフリカ大陸から「輸入」)
②北部:インディオを追放 トップ
*オランダ
1616 ニューネザーランド植民地(→ニューインブランド植民地)
中心都市ニューアムステルダム(→ニューヨークと改称)
第2次英蘭戦争(1665-67)の結果
*イングランド
1607 ニューイングランド植民地13州(-1732)
・移民多数、人工増
*フランス
1608 ケベック(カナダ東部、セントローレンス川河口)建設
1682 ルイジアナ(ミシシッピ川流域)
*三角貿易の構造
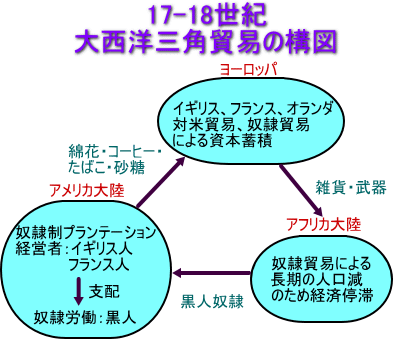
*三角貿易の影響
・アメリカ大陸
北アメリカ:工業生産の発展(北部)
奴隷制プランテーション(綿花、タバコ)の発展(南部)
西インド諸島:奴隷制プランテーション(砂糖、コーヒー)
ヨーロッパに対する経済的従属
・アフリカ大陸:長期の人口流出(1200-2000万人)による経済発展の停滞
・ヨーロッパ:奴隷貿易や砂糖貿易などの利益が、工業化=資本主義発展の前提となる